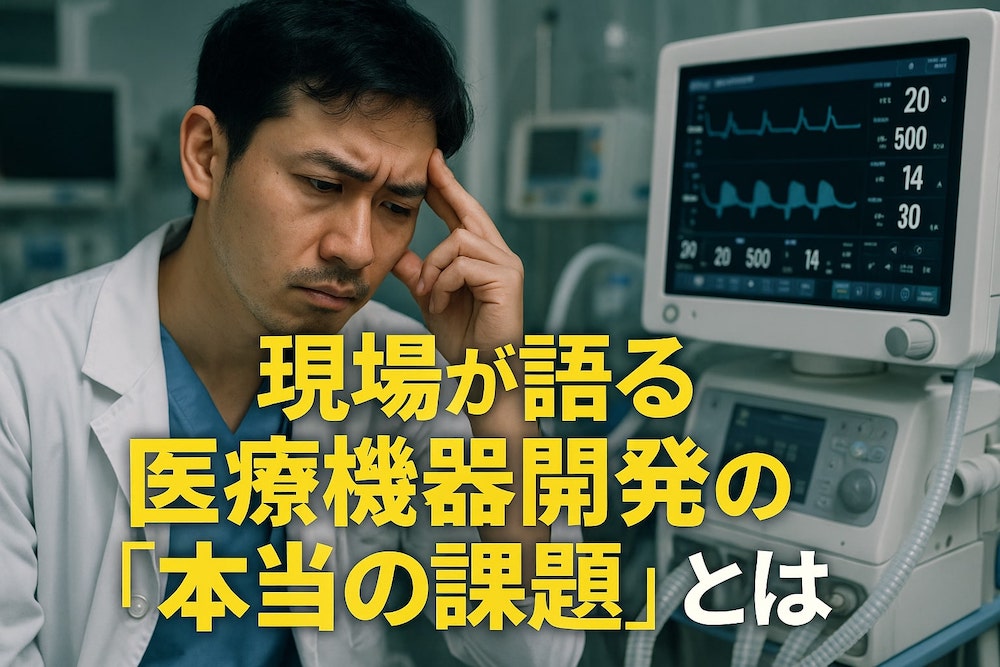現場が語る医療機器開発の「本当の課題」とは
医療機器開発の世界には、表面化しない「見えない課題」が数多く存在している。
私がエンジニアから医療ライターへと転身したのは、まさにこの見えない課題に光を当てたいという思いからだった。
30年近く医療機器開発の最前線で働き、内視鏡や診断装置の開発に携わってきた経験から、技術と医療現場の間には、思いのほか深い溝があることを痛感してきた。
この溝を埋めるためには、現場の声を社会に届けるパイプ役が必要だと考えたのだ。
特に2025年問題を控え、医療機器のイノベーションはますます重要性を増している。
高齢化社会において医療機器は単なる「道具」ではなく、医療の質と効率を大きく左右する存在になりつつある。
しかし、優れた技術が必ずしも現場で活用されるとは限らない。
その理由は何か。
本稿では、30年の開発経験と、現場取材で得た知見をもとに、医療機器開発における「本当の課題」に迫りたい。
現場視点から見る医療機器開発のリアル
開発プロセスの理想と現実
医療機器開発の理想的なプロセスは、「現場の医療ニーズを把握」→「コンセプト設計」→「試作開発」→「臨床評価」→「認証・承認取得」→「市場導入」という流れだ。
しかし、現実はそう単純ではない。
多くの場合、このプロセスは一方通行ではなく、幾度もの試行錯誤を繰り返す螺旋状の道のりとなる。
特に大きな壁となるのが、「臨床評価」から「認証・承認取得」のプロセスだ。
私が関わった内視鏡システムの開発では、最終段階での薬事承認において予想外の指摘を受け、設計変更を余儀なくされたケースもあった。
医療機器開発において理想と現実のギャップを埋めるには、開発初期段階から薬事的な視点を取り入れること、さらには現場の声を継続的に反映させる仕組みづくりが欠かせない。
日本医療研究開発機構(AMED)が提供する「医療機器開発マネジメントにおけるチェック項目」などを活用し、開発全体を俯瞰する視点を持つことも重要だろう。
製品化を阻む”見えない壁”とは
医療機器開発において、技術的な問題以上に製品化を阻むのが、いわゆる「見えない壁」だ。
この壁には主に「組織内の壁」と「組織外の壁」がある。
組織内の壁とは、例えば研究開発部門と事業部門の温度差だ。
優れた技術が開発されても、事業性の観点から製品化されないケースは珍しくない。
一方、組織外の壁は、薬事規制や保険収載の問題、市場受容性の課題などが挙げられる。
私が島津製作所在籍時に経験した例だが、技術的には完成していた新型診断装置が、既存の診療報酬体系に適合せず、製品化を断念したことがあった。
また、医療制度の違いから、国内では普及しても海外では受け入れられない機器も少なくない。
製品化の成否を分けるのは、こうした「見えない壁」をいかに早期に認識し、戦略的に乗り越えるかにかかっている。
製品コンセプト設計の段階から、技術開発と並行して、薬事戦略、知財戦略、そして事業戦略を三位一体で進めることが成功への鍵となるだろう。
こうした課題に対応するため、専門的な医療機器受託開発の経験を持つ株式会社アスター電機のような企業との連携も、効率的な製品化への一つの選択肢といえる。
医師・看護師の声が届かない理由
医療現場の最前線にいる医師や看護師には、日々の診療から生まれる機器への要望や改善アイデアが数多くある。
しかし、それらが開発企業に届くことは意外に少ない。
なぜだろうか。
一つには、医療従事者と開発者の接点が限られていることが挙げられる。
多くの場合、営業担当者を介した間接的なコミュニケーションとなり、生の声が希薄化しやすい。
また、医療従事者側にも「自分たちの要望が製品に反映されるとは思えない」という諦めの気持ちが存在する。
さらに、医療機器メーカーの技術者が現場を訪れる機会が制限されていることも大きな要因だ。
特に医療安全や感染対策の観点から、開発者が手術室などの現場に立ち入ることは容易ではない。
この状況を改善するには、医療機関と企業の連携を制度的にサポートする仕組みや、現場の声を体系的に収集・分析するプラットフォームの構築が必要だろう。
医療機器開発ネットワークなどの取り組みはその一歩だが、より日常的な交流の場が求められている。
ヒアリングで見えた現場ニーズとのズレ
過去5年間、私は医療現場での取材を重ね、多くの医師や看護師から生の声を聞いてきた。
そこで最も印象的だったのは、開発者側が考える「あったら便利」と現場が求める「本当に必要なもの」のズレだ。
例えば、あるメーカーが「最新のAI技術を搭載した診断支援システム」を誇らしげに紹介していたとき、現場の医師からは「それより画像読み込み時間を短縮してほしい」という声が上がった。
また、高機能な医療機器が導入されても、使いこなせずに基本機能しか使われていないケースも多々見られた。
ある病院では、高額な手術支援ロボットが導入されたものの、操作に習熟した医師が少なく、稼働率が低いという問題を抱えていた。
こうした現場のリアルなニーズを知るには、数値化されたデータだけでなく、実際の使用状況や医療従事者の本音を丁寧に聞き取る姿勢が欠かせない。
技術者は「何ができるか」に目を向けがちだが、現場では「何が本当に役立つか」「日常業務にどう組み込めるか」という視点が重視される。
このギャップを埋めることこそが、真に役立つ医療機器開発への第一歩だと言えるだろう。
安全規制とイノベーションのジレンマ
厚労省の規制フレームワークの実態
医療機器開発において、厚生労働省が定める規制フレームワークは避けて通れない関門である。
この規制体系は医薬品医療機器等法(旧薬事法)を基軸に、クラスⅠからクラスⅣまでのリスク分類に応じた承認・認証プロセスが設けられている。
特に注目すべきは、医薬品医療機器総合機構(PMDA)の役割だ。
PMDAは2004年に設立されて以来、医療機器の審査プロセスを担う中核機関として機能している。
近年、PMDAでは審査の効率化や透明性向上に向けた取り組みが進められており、RS戦略相談など開発初期段階からの相談制度も充実してきた。
特に大学やベンチャー企業向けには低額で対面助言を受けられる制度も設けられている。
しかし、依然として規制対応には専門知識と経験が必要であり、中小企業やベンチャーにとっては大きな負担となっている現実がある。
私自身、大手メーカー時代には薬事部門との連携で乗り越えられた壁も、中小企業では専門人材の不足から苦戦するケースを多く見てきた。
規制は必要だが、イノベーションを阻害しない制度設計への不断の見直しが求められている。
「安全第一」が開発スピードを鈍らせる?
医療機器開発において「安全第一」は絶対的な原則だ。
しかし、時としてその原則が新技術導入の速度を遅らせることも事実である。
特に日本では「絶対安全」を求める傾向が強く、米国などと比べて慎重な審査が行われる印象がある。
例えば、私が以前関わった画像診断装置の開発では、ある新技術について米国FDAが先行して承認した一方、日本では追加データの提出を求められ、市場投入に約1年の遅れが生じた。
こうした状況は、リスクとベネフィットのバランスをどう考えるかという本質的な問題に関わっている。
過度に慎重すぎる姿勢は患者が新技術の恩恵を受ける機会を遅らせることにもつながる。
一方で、安全性確保は医療機器の大前提であり、単純に規制緩和を進めればよいわけではない。
このジレンマを解消するには、早期からの当局との対話や、リスクに応じた柔軟な審査プロセスの設計が重要だ。
近年導入された「条件付き早期承認制度」や「特定臨床研究制度」は、このバランスを取るための一歩と言えるだろう。
安全性と革新性の両立は、技術者だけでなく、規制当局や医療現場も含めた社会全体で考えるべき課題である。
現場導入に立ちはだかる承認プロセスの壁
医療機器が開発され、薬事承認を得たとしても、実際の医療現場への導入には別の壁が存在する。
その最たるものが、保険収載と呼ばれる診療報酬上の評価だ。
優れた医療機器でも、適切な保険点数が付かなければ病院経営の観点から導入が見送られるケースは少なくない。
特に新しい技術カテゴリーの場合、既存の診療報酬体系に当てはまらず、保険収載までに長い時間を要することがある。
私が経験した超音波診断装置の新技術は、臨床的有用性が認められながらも、保険収載までに約3年を要した。
また、承認後の市場導入プロセスにおいては、医療機関の予算サイクルや意思決定プロセスも大きな影響を与える。
多くの病院では年度予算で大型機器の購入が決定されるため、タイミングを逃すと1年近く導入が遅れることもある。
こうした「市場への壁」を乗り越えるには、開発初期から出口戦略を見据えた計画立案が欠かせない。
保険戦略や市場導入戦略を技術開発と並行して進め、薬事承認取得後にスムーズに市場浸透できる準備を整えることが重要だ。
製品として形になっても、現場で使われなければ意味がない—この当たり前の事実を、開発者は常に意識すべきだろう。
技術と現場が乖離する理由
設計者と使用者の”言語の違い”
医療機器開発における最も根本的な課題の一つが、設計者と使用者の「言語の違い」だ。
技術者は性能や機能を中心に思考する一方、医療従事者は臨床的価値や使い勝手を重視する。
同じ「使いやすさ」という言葉でも、技術者は操作性や UI の洗練度を指すことが多いが、医師や看護師にとっては診療ワークフローへの統合しやすさを意味することが多い。
私が島津製作所在籍時に経験した例だが、技術陣が自信を持って開発した高機能な画像処理システムが、実際の放射線科医からは「日常業務で使いこなす時間がない」と評価されたことがある。
この「言語の違い」を埋めるには、単なる要件定義の精緻化だけでは不十分だ。
開発プロセスの早期段階から医療従事者を巻き込み、共同で課題設定から行うことが重要となる。
最近では、ユーザー中心設計(UCD)やデザイン思考の手法を導入する企業も増えてきているが、形式的な導入にとどまらず、真の協創関係を構築することが求められている。
技術者と医療者が互いの「言語」を学び合い、共通理解を深める場づくりこそが、乖離を埋める第一歩となるだろう。
病院での導入支援不足がもたらす混乱
優れた医療機器が開発されても、病院での導入支援が不十分だと、その真価を発揮できないことがある。
私が取材した複数の病院では、高度な医療機器が導入されたものの、十分な操作トレーニングが行われず、機能の一部しか活用されていないケースが散見された。
ある大学病院では、最新の手術支援ロボットを導入したものの、十分なトレーニング体制が整わないまま運用を開始し、当初は予想よりも長い手術時間を要する結果となっていた。
また、新しい機器の導入は、既存の診療ワークフローの変更を伴うことが多い。
しかし、この「変更管理」への支援が不足していると、医療現場に混乱をもたらす要因となる。
技術革新のスピードが加速する中、医療従事者が新技術に適応するための時間と支援はますます重要になっている。
メーカーは単に機器を販売して終わりではなく、導入後の継続的なサポートや教育プログラムの提供が求められる。
病院側においても、新技術導入の際には操作研修だけでなく、診療プロセス全体の見直しを含めた計画的な導入が必要だ。
技術と人をつなぐこの「最後の1マイル」をいかに設計するかが、医療機器の真の価値を決定づける要因となっている。
ユーザビリティ vs. 技術的完璧さ
医療機器開発において、しばしば「技術的完璧さ」と「ユーザビリティ」が対立する場面がある。
技術者は性能の向上や機能の充実に力を注ぎがちだが、実際の医療現場では単純明快な操作性や堅牢性が重視されることが多い。
私が経験した内視鏡システムの開発では、画質向上のために複雑な操作パネルを設計したところ、現場からは「緊急時に迷わず使えるシンプルさが欲しい」という声が上がった。
特に救急医療や手術室など、ストレス下での使用を想定した場合、「99%の精度と簡単な操作」の方が「99.9%の精度と複雑な操作」より価値が高いケースもある。
また、技術的には最先端でも、現場の様々な制約(スペース、電源、ネットワーク環境など)に適合しなければ活用されない。
この課題に対処するには、開発プロセスの早期から実際の使用環境を詳細に調査し、現場の制約条件を設計要件として取り込むことが重要だ。
「最高の技術」より「最適な技術」を目指す姿勢こそが、真に価値ある医療機器を生み出す鍵となる。
技術者は自らの専門領域に閉じこもるのではなく、「なぜこの技術が必要なのか」「誰のためのものなのか」という本質的な問いを常に念頭に置くべきだろう。
現場と社会をつなぐために必要なこと
技術者がもっと現場に足を運ぶべき理由
医療機器開発において、技術者が現場に足を運ぶことの重要性は幾度となく強調されてきた。
しかし、その本当の理由は単なる「ユーザーの声を聞く」ということではない。
現場に身を置くことで初めて見えてくる医療の複雑な生態系と、そこに存在する無数の暗黙知を体感することにある。
例えば、私が若手エンジニア時代に手術室で内視鏡の使用状況を見学した際、医師が機器を想定外の方法で使用している場面に遭遇した。
それは仕様書には書かれていない「現場の知恵」だったが、その観察がその後の設計改良につながった。
また、現場を訪れることは、開発者自身の「当事者意識」を高める効果もある。
書類上の症例報告と、目の前で治療を受ける患者さんを見ることでは、開発への動機づけが根本的に変わってくる。
実際、現場訪問経験のある開発者とそうでない開発者では、同じ機能要件に対する解釈や優先順位づけに明らかな違いが生じることがある。
「百聞は一見に如かず」という言葉通り、技術者が現場の空気を肌で感じることは、文書化されたデータやヒアリングでは得られない価値をもたらす。
制度上の制約はあるものの、可能な限り現場体験の機会を増やす工夫が求められているのではないだろうか。
「ものづくり愛」だけでは解決できない課題
医療機器開発には、技術への情熱や「ものづくり愛」が欠かせない。
しかし、それだけでは解決できない課題が確実に存在する。
例えば、どんなに優れた製品を開発しても、医療経済性や保険制度との適合性がなければ普及は難しい。
私が経験した例では、画期的な診断技術を搭載した機器が開発されたものの、保険点数が付かず、結果として経営的に導入できない病院が多かった。
また、医療機器は単体で機能するのではなく、病院全体のシステムや既存機器との連携が必要となる。
特に近年のデジタル化の波の中で、相互運用性(インターオペラビリティ)の問題はますます重要になっている。
医療機器は「単品の道具」ではなく「医療エコシステムの一部」として機能することが求められているのだ。
さらに、グローバル展開を考えると、各国の規制対応や文化的背景への配慮も欠かせない。
これらの課題に対処するには、技術開発と並行して、制度設計や標準化活動、さらには医療経済学的な視点も含めた総合的なアプローチが必要だ。
「ものづくり愛」を原動力としつつも、より広い視野で医療機器の社会実装を考える姿勢が、これからの開発者には求められている。
政策・業界・教育の連携によるブリッジ構築
医療機器開発における「現場と技術のギャップ」を埋めるには、個別企業の努力だけでは限界がある。
政策立案者、業界団体、そして教育機関を含めた幅広い連携が必要だ。
例えば政策面では、厚生労働省の規制と経済産業省の産業振興策の連携強化が求められる。
両省の取り組みは近年徐々に歩み寄りを見せているが、現場からは「縦割り行政の壁」を指摘する声も少なくない。
業界団体においては、日本医療機器産業連合会(医機連)などを中心に、企業の枠を超えた情報共有や人材交流の場が設けられつつある。
こうした取り組みは「競争と協調の適切なバランス」を模索する試みとして評価できる。
特に注目すべきは教育機関の役割だ。
医学部と工学部の連携プログラムや、臨床現場を体験できるインターンシップなど、早期から「異分野交流」を経験できる機会が増えている。
大阪大学の「医工連携」プログラムなどは、その先駆的事例と言えるだろう。
医療機器開発に携わる人材には、専門性の深さと同時に、境界を越える力が求められる。
そのためには、制度や組織の枠組みを超えた「ブリッジビルダー」の育成が急務だ。
現場と技術、規制と産業、医学と工学—これらの間に立ち、翻訳者として機能できる人材こそが、これからの医療機器イノベーションの鍵を握っている。
若い世代へのメッセージ
医療業界を志すエンジニアへのエール
医療機器開発を志す若いエンジニアの皆さんへ。
この道は決して平坦ではないが、その分だけやりがいと社会的意義に満ちた領域だと断言できる。
私は30年以上この世界に身を置き、時に挫折も味わいながらも、自分の関わった機器が患者さんの治療に役立つ瞬間を見るたびに、この道を選んだことを誇りに思ってきた。
医療機器開発の魅力は、技術的チャレンジと人道的価値の両立にある。
最先端の技術を駆使しながらも、最終的には「人を救う」という明確な目的に収束する仕事は、他の産業ではなかなか味わえない充実感をもたらす。
これから医療機器開発を目指す方々には、いくつかのアドバイスを送りたい。
まず、自分の専門分野だけでなく、隣接領域への好奇心を持ち続けること。
特に生体工学、材料科学、ソフトウェア工学などの境界領域は、これからのイノベーションの源泉となるだろう。
次に、医療現場の実態を知る機会を積極的に求めること。
可能であれば、大学時代から医工連携プログラムや病院見学などに参加し、医療の生態系を体感してほしい。
そして最も重要なのは、「誰のために、何のために」という問いを常に念頭に置くことだ。
技術開発の細部に没頭する中でも、最終的な目的を見失わない姿勢が、真に価値ある医療機器を生み出す原動力となる。
医療機器開発は、忍耐と情熱を要する長い旅路だ。
しかし、その先にある「人の命と健康に貢献する」という達成感は、何物にも代えがたい報酬となるだろう。
「現場を忘れるな」の真意とは
私が技術者として歩み始めた頃、故・中村技師長から贈られた「技術者は現場を忘れるな」という言葉は、30年経った今も私の心に刻まれている。
しかし、この言葉の真意を本当に理解できたのは、数々の成功と失敗を経験した後のことだった。
「現場を忘れるな」とは、単に「ユーザーの声を聞け」ということではない。
それは、技術が最終的に使われる場所、人々の命が守られる場所、医療という営みが行われる場所の「文脈」を常に意識せよという教えだ。
例えば、ある救急医療用モニターの開発で、私たちは高精度な測定機能を誇りに思っていた。
しかし、救急現場で実際に使用された際、救急車の振動で誤作動を起こすという致命的な問題が発覚した。
それは私たちが「救急車という特殊環境」を十分に考慮していなかったためだった。
「現場を忘れるな」とは、技術の先にある「人間の営み」全体を視野に入れよという戒めであり、同時に技術者としての社会的責任を自覚せよという叱咤でもある。
技術開発においては、ともすれば「どうやってつくるか」という手段に意識が集中しがちだ。
しかし本当に大切なのは「なぜつくるのか」「誰のためにつくるのか」という目的意識を失わないことだろう。
「現場を忘れるな」—それは単なる技術哲学ではなく、医療機器開発の根幹を支える実践的な指針なのだ。
技術の未来に必要な”人間の視点”
AIやロボティクス、IoTなどの急速な技術進化によって、医療機器開発の可能性は大きく広がっている。
機械学習による診断支援や手術支援ロボット、遠隔モニタリングデバイスなど、かつて夢物語だった技術が次々と実用化されつつある。
しかし、こうした先端技術の導入において最も見落とされがちなのが「人間の視点」ではないだろうか。
複雑化する技術は時として、本来あるべき目的を見えにくくする。
例えば、AIが生成した診断結果を医師がどう解釈し、患者にどう説明するか—このプロセスを支援する視点が不足している機器は少なくない。
また、高度な自動化が進む中、技術の「ブラックボックス化」が進み、医療者の技術理解を超えた領域が広がっている。
これは時に、現場での適切な活用や、万一のトラブル時の対応を困難にする。
京都大学での講演で某教授が語っていたように、「技術は人間の判断を支援するものであって、代替するものではない」という視点は、これからの医療機器開発において決して忘れてはならない原則だ。
人間中心設計(Human-Centered Design)の考え方を取り入れることで、技術の恩恵を最大化しつつも、その中心に常に患者と医療者を置く視点が重要となる。
技術革新のスピードが加速する今だからこそ、「人のための技術」という基本に立ち返ることが、医療機器開発の未来を切り拓く鍵となるだろう。
私は技術者からライターへと転身したが、その根底にあるのは「技術と人間をつなぐ」という使命感だ。
若い技術者たちには、先端技術の追求と同時に、その技術が最終的に人間の手に届いたとき、どう使われ、どう受け止められるかという想像力を大切にしてほしい。
まとめ
医療機器開発の現場から見えてきた「本当の課題」は、技術そのものよりも、技術と人をつなぐ「橋渡し」の不足にあった。
開発プロセスにおける現場との乖離、薬事規制とイノベーションのジレンマ、製品導入時の支援不足など、幾重にも重なる課題が、優れた技術の社会実装を阻んでいる。
これらの課題解決には、個別企業の努力だけでなく、産学官連携によるエコシステムの構築が欠かせない。
日本の医療機器産業は、高い技術力を持ちながらも、グローバル市場でのシェアは必ずしも高くない。
その要因の一つが、「技術先行」ではなく「ニーズ先行」の開発アプローチの不足だろう。
今後の超高齢社会に向けて、医療機器への期待はますます高まっている。
2025年の団塊世代の後期高齢者入りを前に、医療の効率化や質の向上に貢献する機器の開発は急務となっている。
そのためには、技術シーズの追求だけでなく、現場のニーズを丁寧に拾い上げ、それを形にする「翻訳者」としての役割が重要だ。
私自身、メーカーのエンジニアからライターへと転身したのも、この「翻訳者」としての使命感からだった。
技術と制度、そして何より人をつなぐ視点こそが、これからの医療機器開発に求められる次の一歩だと確信している。
最後に、医療機器開発に携わるすべての方々に伝えたい。
我々の仕事は、単に「モノをつくる」ことではない。
患者さんの命と健康を支え、医療現場に新たな可能性をもたらす「架け橋」を築くことなのだ。
技術の先に人の顔を見る想像力と、社会に価値を届ける情熱が、医療機器開発の真髄なのではないだろうか。
最終更新日 2025年4月25日 by erum